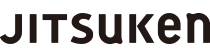| ■いつ? |
|---|
| 2003年11月13日 |
| ■どこで? |
| 国立国語研究所 |
| ■誰が? |
| 国立国語研究所 |
| ■何をした(する)? |
| 外来語(カタカナ語)の言い換え案を十三日、二回目の最終提案四十七語を発表した。 |
| ■なぜ? |
| 官公庁の文書などでわかりにくいカタカナ語の多用に警鐘を鳴らすため。 |
| ■どのように? |
|
・第一回と合わせ、これで計百九語の言い換え例が示された。同研究所が調べたところ、提案を始めてから、行政白書の記述などに改善が見られることがわかった。
・同研究所「外来語」委員会は、昨年十二月に第一回言い換え提案を中間発表。この前後で、文部科学、厚生労働、外務、農林水産、経済産業の各省の白書の記述が変化したかどうか調査した。 ・厚生労働、外務、農林水産、経済産業の各省のうち「劇的に変化した」と評価されたのが、文部科学白書。今年二月に発行された二〇〇二年度版を、昨年一月発行の二〇〇一年度版と比べると、「バリアフリー」など四十九のカタカナ語に、これまでなかった欄外の脚注が付けられていた。「~のニーズに応え」といったカタカナ語を使う必然性がない表現もほとんどなくなった。 ・厚生労働白書は、昨年九月発行の二〇〇二年版で目立った「ピーク」「シフトする」などの表現が、今年八月発行の二〇〇三年版では消え、「インフォームド・コンセント(説明と同意)」のように注釈を付ける工夫も見られた。外務省の外交青書にも、なじみの薄いカタカナ語に脚注が付くようになった。
・一方、経産省の通商白書と農水省の図説食料・農業・農村白書には、あまり変化がなかった。経産省は「努力はしているが、世界で通用する経済用語には英語が多いので難しい」としている。 |